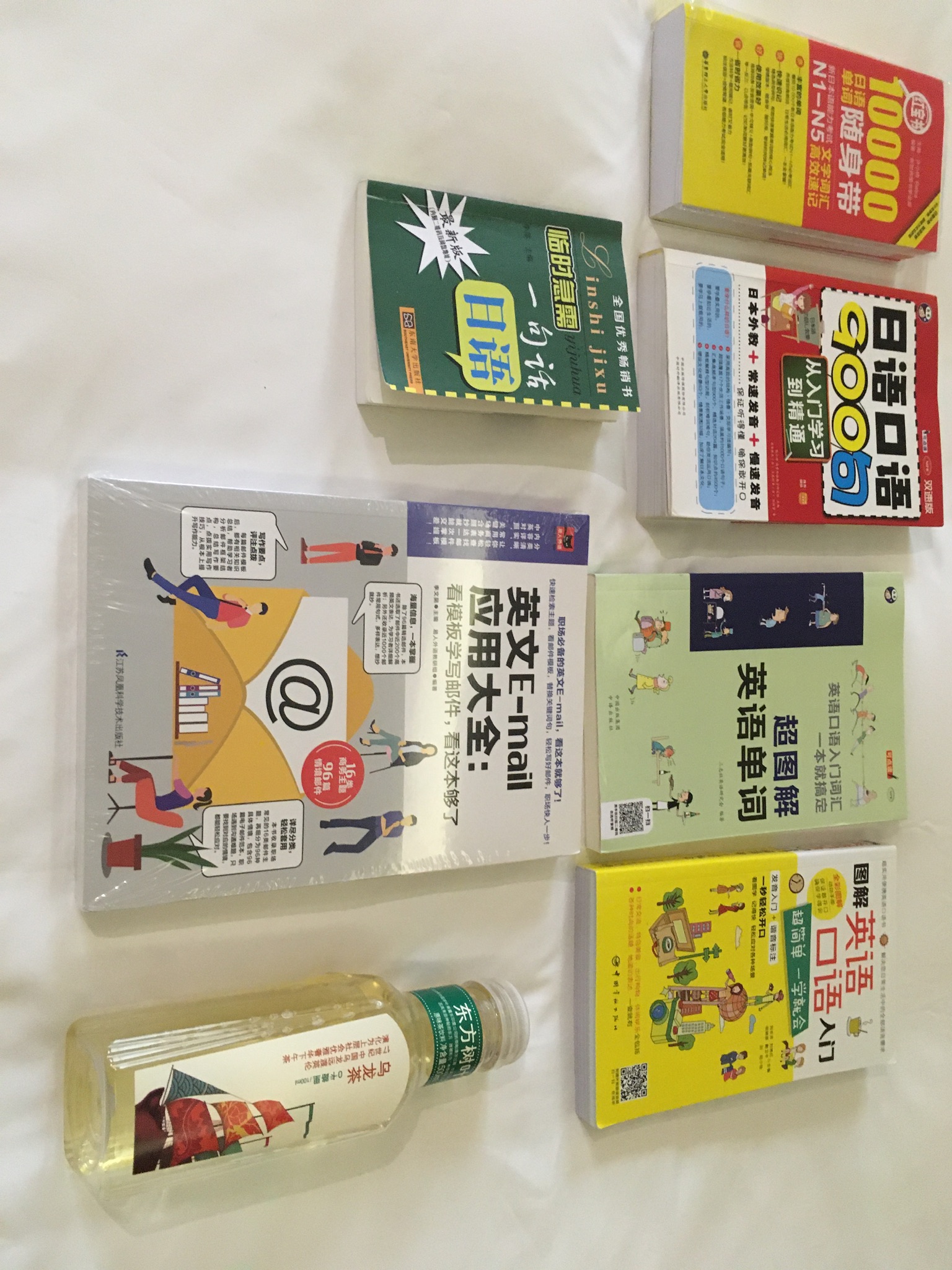昨年書きかけの記事を更新。
旅に出た時の感覚があるうちに更新。
26、27歳の挑戦
「真剣に酔狂なことをして生きてみたい」
乗りあいバスを使いながら、可能な限り陸地を伝って
世界を回ってみたい
作者、沢木耕太郎氏の挑戦。
***
ようやく、「深夜特急」を3巻全てを読んだ。
この本を知ってから今年(2019年)まで、
第1巻しか読んでいなかった。
なぜなら、香港・マカオ編での熱狂が刺激的で、
その部分しか読む気が起きていなかったからだ。
この本自体は、私にとって、
単なる海外旅行を誘発する起爆剤であるだけでなく、
語学を学ぶツールとしても活躍した。
実際に現地で第1巻の繁体字版、簡体字版も購入し、
語学学習にも役立っている。
この本に触発されて世界一周や旅行に出かける人多い。
私は、「世界一周」に憧れるというよりも、
それぞれの国において、そこに住む人々が過ごす
ありのままの日常について考えることがより好きになった。
以下、読んで感じたことを箇条書きで記す。
■語学の視点
→著者が大学で学んだスペイン語が
第三巻のヨーロッパ編で活きていた。
やはり語学は生き方の幅を拡げられると感じた。
■共感
留学をしていて感じた、お金がないことによって
自由が制約される感覚はよくわかった。
■挑戦と日常
27歳の作者が行った、冒険譚は20代の青春を象徴し
キラキラと輝いている。
バスで地球を一周するという旅は、
理論上はできるけど、“普通はそんなことを考えもしない”
というユニークな挑戦だ。
観光地ではなく、日常の姿を見たい、当たり前の生き方とは何か、
筆者は生活のバスを使って移動することを好んでいた。
■無責任であること
責任のない旅人。
☆読んだことで、
・今回の台湾旅を記録に残そうと思わせてくれた
・+韓国旅へと私を誘った。
■旅から得る問い
将来という可能性がある固定した何かに
決まりつつある、ということ、
それに対して問いを投げる、ということ。
■旅のような生き方とはー責任からの一時的な解放
日々、”あえて”目的を持たずに、生きること。
第1巻P.11の
「たとえば朝、ベッドの上で眼を覚ますと、今日一日どうしようかと考える」
→自分で自分の行動を決めることができる
→生物として、生き残るために必要な“目的”意識から解放されている
*目的とは、生存するために必要なことがら
共感する。
「キッチリ計画を立て、その通りに動く」という旅なんて絶対したくない
第2巻P.64「(中略)私は、風に吹かれ、水に流され、偶然に身を委ねて
旅することに、ある種の快感を覚えるようになっていた。」
なるべく最低限。航空券を取る。ホテルの予約をする。
※ただし、このような期間は永遠ではなく限られた時間である
なんの責任もないから、制約がない(少ない)からこそできること、
すなわち、自由であるということだ
第二巻P.222
「旅にとって大事なのは、名所でも旧跡でもなく、
その土地で出会う人なのだ。」
留学でも感じていたこと。
景色、背景は珍しくなくなる。
☆旅が終わった時の感覚
→非日常が終わる瞬間。
→制約が再び与えられる生き方へ。
☆旅の中での矛盾
自由になったはずが、
倹約。すなわち、お金の制約に縛られて生活が制限されている
■旅の後、夢の後、留学の後
第2巻P.246
「故郷で待っているのは、「真っ当な生活」だけだ。それも悪くはないが、
自分がそのような生活に復帰することができるのかどうか、不安がない
わけではない。復帰できたとしても、果たして「真っ当な生活」に耐えていかれるだろうか」“”
この視点は、昔話の竜宮城しかり。
正直に(中国)留学後、社会に馴染むことが難しかった。
就職斡旋業者の言葉も、理解が難しかった。
そんなオレにチャンスが待っていた。
「当たり前を壊し、自分で切り開け。」
時代を動かす潮流を間違いなく作り、想いを残してこの世を去った、国力に等しい人がいた。
創業者さんの熱い意思を自分は継ぎたい。心から思った。
なぜなら、その方は私の考えるカッコイイ大人の像だったから。
■なぜ、命に対して鈍感になるのか
→本来、’働かないと生活ができない‘
→大部分の人口と同様に
生物として当然な、生き残る(サバイバル)環境にあるから。
生き残る、という感覚が求められている
☆“目的思考”とは、サバイバルへの打算である。
いかに、今という状況から効率的に、合理的に思考するか。
☆ギャンブルへの魅了
第1巻P.137
→論理を否定する
→中途半端な賢明さから脱して
徹底した酔狂の側に身を委ねる
沢木さんの当時の熱狂は、
簡体字であろうと、繁体字であろうと伝わってくる。